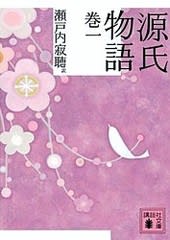
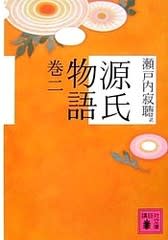



誰もが憧れる源氏物語の世界を、気品あふれる現代語に訳した「瀬戸内源氏」。文学史に残る不朽の名訳で読む華麗なる王朝絵巻。巻一では、光源氏の誕生から、夕顔とのはかない逢瀬、若紫との出会いまでを収録。すべての恋する人に贈る最高のラブストーリー。
瀬戸内寂聴 訳
出版社:講談社(講談社文庫)
源氏物語が成立してから千年が経つわけだが、なぜ千年経っても、この作品が読み続けられているか、読んでみて納得することができる。
それは単純におもしろいからにほかならない。
物語の展開はドラマチックだし、登場人物の心理描写は精緻で、その苦しみや悩み、打算などが読み取れ、ときに共感を、ときに反発を呼び起こしてもくれる。
個人的には「帚木」~「夕顔」までの空蝉の心理描写には惹かれたし、「若紫」「葵」「須磨」「明石」「蓬生」あたりは物語としておもしろい。「末摘花」は末摘花のあまりの扱いのひどさに、ちょっと泣けてくる。
キャラクターの描き分けもできていて、どの登場人物も、好悪は別として、個性を感じさせる人たちばかり。
王朝物語ということもあり、当時の雰囲気がよく出ているし、さすがに格調も高い。
もちろん合わない部分もあることはある。
当時の、通い婚というか、夜這い婚というか、その風習が馴染めないし、半ば強姦で女と関係を結ぶという方法に違和感を覚える。
男に強姦された後の、女たちのショック状態の心理は、かなり生々しく感じられ(特に「葵」での若紫)、正直読んでいてつらい。
また物語の展開も、ここはよけいだなと感じる部分があったり、間延びしているな、と思う部分もなくはない。
もっと率直に言うなら、少し長すぎる。全十巻読むのに、長期休暇をはさんでも、一ヶ月かかったという時点で、その分量は推して知るべしだ。
だがそれらも含めて、言うなれば、『源氏物語』の魅力でもある。
世間的には、光源氏の誕生から栄華を極めるまでを描いた、「桐壺」~「藤裏葉」を第一部。
女三宮の降嫁から光源氏の死までを描いた、「若菜上」~「雲隠」までを第二部。
宇治十帖を含む薫たちの物語を描いた、「匂宮」~「夢浮橋」までを第三部と見るようだ。
寂聴は第二部の「若菜」を誉めていたし、世間的には第三部の宇治十帖を誉める人も多いらしい。
だが、個人的には第一部が一番おもしろいと思った。
登場人物のキャラクター、そのメロドラマ性など、目を引く部分も多い。
一度ちゃんと読んでおいてよかったな、と感じさせる、名作である。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかの『源氏物語』の感想
『源氏物語 巻六・巻七(若菜上~紅梅)』
『源氏物語 巻八~巻十(竹河~夢浮橋)』
●追記(あるいはキャラクター論)
源氏物語には個性的なキャラクターが多く、紫式部が精魂込めてキャラクターを創造したであろうことが、読んでいても伝わってくるのが魅力だ。
だがやはり紫式部も女性。そのため、女性キャラに重点を置いていると感じさせる部分が多い。
もっともそれは女性が当時弱い立場だったということも大きいだろう。
男に捨てられたら、それだけで暮らしも窮乏する。同じ女性として同情していたのかもしれない。
だが同時に女性陣を魅力的に描いたのは、多分、男どもの軽薄さと、浮気癖に、紫式部が失望していたからではないかとも感じられるのだ。
巻十で瀬戸内寂聴も指摘していることではあるが、「男はせいぜいこの程度よ」と思っていたのかもしれない。
それを個人的に強く感じたのは、玉鬘を巡る男性陣の節操のなさだ。
光源氏は、玉鬘の弱い立場を利用して、自分の家に引き取ると、体に触りまくるというセクハラをくり返すし、裸になって玉鬘の横に寝転がり、犯そうととする始末(泣いて拒まれたからやめたけど)。
加えて、処女は面倒なので、嫁にでもやって男女のことがわかった後に、お忍びで浮気をしよう、って感じのことを(僕の意訳ではあるけど)考えるから、性質が悪い。
バカじゃねえの、と読んでいて思ってしまう。
柏木たちはあれだけ熱心に玉鬘のもとに通い詰めて、求婚したのに、兄妹であるとわかると否や、手のひらを返したように、冷たい態度を取る。
くそマジメなだけが売りの(一応誉めている)夕霧は、玉鬘が妹でないとわかるとすぐに、言い寄ったりと、態度の豹変ぷりが露骨すぎる。
紫式部は男たちの立ち居振る舞いを、作中で何度も誉めている。
だがそんな男たちの内実を、心の底では軽蔑していたのかもしれない。
一方の女性キャラはやはり魅力的。
たとえば最初の方に登場する空蝉。
彼女は源氏と心ならずも結ばれるわけだが、その後、源氏の魅力に惹かれ心がゆれていく。彼女は夫を軽蔑しているし、源氏を好きになりかけてもいるのだから、相手に傾いてもおかしくないはずだ。
しかし彼女は、人妻であるという自分の立場を守り、徹底的に源氏の誘惑を退けようとする。
だが退けながらも、ゆれる心はどうあっても、消えることはない。
その心理描写が巧みで、なかなか読ませるものがある。
そのゆれる描写に触れたおかげで、すぐに空蝉が好きになってしまった。
紫の上も魅力的に描かれている。
初登場時の、子どもらしい姿はいかにも愛らしいし、才気走っていながら、行動はまだ子供じみているところを描く筆は、寂聴も指摘するように、非常に冴えている。
大人になってからの紫の上も魅力的だ。
特に源氏の浮気に対して、嫉妬し、むくれるところなどはおもしろい。
源氏に対して、口を利かなかったり、皮肉を言うことが多く、源氏はその機嫌を取ろうと、あれこれと手を尽くすシーンが頻出する。
そういうシーンを読んでいる間、ガンバレ、紫、と勝手に応援してしまう。
そんな風に応援したくなるような雰囲気が、紫の上にはあるのだ。
ほかにも、千年前の萌えキャラとでも言うべき存在の、夕顔。
正妻を呪い殺すほどの重たい情念を持っていて、強烈な個性を感じさせる、六条御息所。
自分の身の程をわきまえて、ちょっと卑屈にさえ見えるところが逆に印象的な、明石。
無口で野暮ったくて、堅苦しい行動しか取れず、多分作者からも愛されてなさそうで、それが本当にかわいそうな、末摘花。
ある意味若く、ある意味ではイタく、滑稽で悲しく、それゆえに愛すべきキャラの、源典侍。
プライドの塊のような、葵の上。
おっとりしていて、人間的にもかなりできた人という印象を残す、花散里。
空気を読めないところが魅力的な、近江の君、など。
すてきな女性陣が多く、印象的。
源氏物語は、光源氏の物語だが、同時に女性たちの物語でもあるのだろうと感じさせられるキャラクター群である。










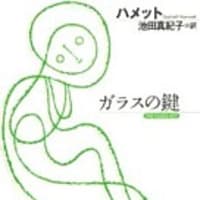

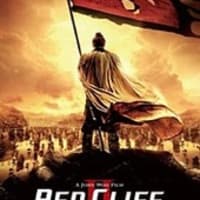
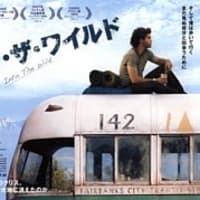
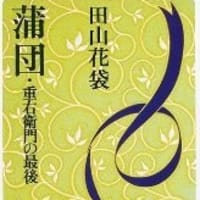
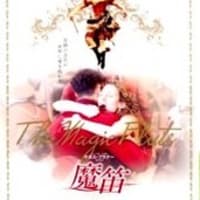
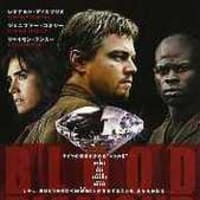
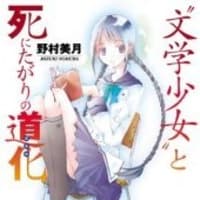
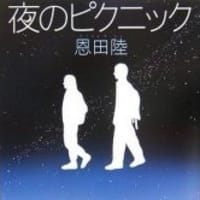

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます